インドネシアなどの東南アジア諸国で大豆などをテンペ菌で発酵させる醗酵食品である。味は納豆に似ており、弱い臭気があるが、糸を引くことはない。
テンペを作るにはまず大豆を丸ごと煮てやわらかくし、砕いたりつぶしたりする。酸味料(多くは酢)を加え、テンペ菌と呼ばれるRhizopus oligosporus(接合菌に属するクモノスカビの一種)を含むタネを混ぜる。薄くのばして30℃程度で約24時間醗酵させる。良質のテンペでは豆が白い菌糸の層と織り合わされた状態となる。醗酵時間が長すぎると表面に黒い胞子が生成するが、これには害はない(質は落ちる)。アンモニア臭の少ない方が良質である。
テンペでは大豆タンパク質が醗酵によって消化されやすくなっており、また不消化でガスの原因となるオリゴ糖が特に減少している。伝統的なテンペ屋で用いるタネにはテンペ菌以外にも有用な細菌(ビタミンB12などのビタミンを生成する)を含むことが多いが、先進国では純粋培養したテンペ菌を用いるのが普通である。テンペは食物繊維も多く含む。
大豆以外の豆や穀物から作られるテンペもある。特殊なものとしてはココナッツから作られるTempe bongkrekがあるが、これには有害な微生物が混入して毒素を生成する場合がある。しかし豆や穀物のテンペではこのようなことは起きない。豆や穀物のテンペで、正常な色・質感・においがあれば安全である。
調理には、小さく切り、塩水や魚醤などに漬けて油で揚げることが多い。調理したテンペはそのまま食べたり、チリ、スープ、シチューなどに入れる。テンペは複雑なにおい(ナッツ様、肉様、あるいはキノコ様)を有する。テンペは冷凍することもでき、現在では多くの先進国で入手できる。
インドネシアでは他にこれに類似した食品としてダケとオンチョムが知られている。大豆、ココナッツなどの材料を問わず、クモノスカビを用いて発酵させたものをテンペ、クモノスカビと同じ接合菌のケカビを用いて発酵させたものをダケ、子嚢菌のアカパンカビを用いて発酵させたものをオンチョムと呼ぶ

テンペを作るにはまず大豆を丸ごと煮てやわらかくし、砕いたりつぶしたりする。酸味料(多くは酢)を加え、テンペ菌と呼ばれるRhizopus oligosporus(接合菌に属するクモノスカビの一種)を含むタネを混ぜる。薄くのばして30℃程度で約24時間醗酵させる。良質のテンペでは豆が白い菌糸の層と織り合わされた状態となる。醗酵時間が長すぎると表面に黒い胞子が生成するが、これには害はない(質は落ちる)。アンモニア臭の少ない方が良質である。
テンペでは大豆タンパク質が醗酵によって消化されやすくなっており、また不消化でガスの原因となるオリゴ糖が特に減少している。伝統的なテンペ屋で用いるタネにはテンペ菌以外にも有用な細菌(ビタミンB12などのビタミンを生成する)を含むことが多いが、先進国では純粋培養したテンペ菌を用いるのが普通である。テンペは食物繊維も多く含む。
大豆以外の豆や穀物から作られるテンペもある。特殊なものとしてはココナッツから作られるTempe bongkrekがあるが、これには有害な微生物が混入して毒素を生成する場合がある。しかし豆や穀物のテンペではこのようなことは起きない。豆や穀物のテンペで、正常な色・質感・においがあれば安全である。
調理には、小さく切り、塩水や魚醤などに漬けて油で揚げることが多い。調理したテンペはそのまま食べたり、チリ、スープ、シチューなどに入れる。テンペは複雑なにおい(ナッツ様、肉様、あるいはキノコ様)を有する。テンペは冷凍することもでき、現在では多くの先進国で入手できる。
インドネシアでは他にこれに類似した食品としてダケとオンチョムが知られている。大豆、ココナッツなどの材料を問わず、クモノスカビを用いて発酵させたものをテンペ、クモノスカビと同じ接合菌のケカビを用いて発酵させたものをダケ、子嚢菌のアカパンカビを用いて発酵させたものをオンチョムと呼ぶ

PR
技術には、様々な扱われ様があり、それは単なる技術上のものと思想が絡んだものとがある。
平塗り…塗り斑無く、平たい状態に塗り上げる事。
ハッチング…引っかいたり、面相筆を使ったりして、細い線で描いていく事。
インタリオ…陰刻法。凹を刻む方法。削るハッチング。
クロスハッチング…その細線を交差させた重層や、色んな色線を重ねる事
マスキング…テープで支持面を保護し、保護されていない所だけに塗布する事。
ステンシル…その保護の計算織面仕様によって、模様を創る事。
デカルコマニー…張り合わせた絵の具の引きや型を使う、型押しモデリング。
フロッタージュ…物の型を起こす技術。
コラージュ…紙を張り合わせ、絵画にする、また絵画と一体化させる事。
アッサンブラージュ…立体物を張り合わせ、絵画にする、また絵画と一体化させる事。
ヒディング…下地の跡を少し隠し、その痕跡を魅力に変える技術。
モデリング…媒質塑形。状態は様々で、色々な状態が望める技術。「応物象形」
ポワリング…絵の具を垂らす技術。特殊なクセがいる。描写と中々噛みにくい。
アクションペインティング…絵の具を叩きつけたり、振り回したりする技術。
ドリッピング…絵の具の玉を振り落とす技術。前述した2つとは同種類になる。
透かし
暈し
ブラッシュストローク
ドライブラッシュ
基礎技術
着色(反復)ティンティング
着色(塗布)ペインティング
下図 エスキース
輪郭特定 プロフィリ
輪郭調整 コントリオーニ
下線主線確定 カルトーネ
彩色 カラーレ
キアロスクーロ(明暗画)
インパスト(上層厚塗り)
インプリマトゥーラ(有色下地)
グレージング(単色層)
カマイユ(有色下地上単色画)
グリザイユ(白~黒階調画)
エボッシュ(彩色下絵)
グラッシ(薄塗り重層画)
ハッチング(線描)
クロスハッチング(交差線描)
スカンブリング(仕上げ平塗り・技術)
ベラトゥーラ(仕上げ平塗り・表現)
ベラメンティ(仕上げ平塗り・細密化)
リリエーヴォ(盛り上げ効果)
プレパレーション(地塗り)
ヒディングパワー(色層力)
コンポジジション(色面バランス分割)
クロワゾネ(仕切り色面)
アラプリマ(直接描き ・喜踊躍動) primaria
模 イミテーション
再現 リプレゼンテーション
再復 レストレーション
復元 レノバティオ
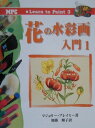
平塗り…塗り斑無く、平たい状態に塗り上げる事。
ハッチング…引っかいたり、面相筆を使ったりして、細い線で描いていく事。
インタリオ…陰刻法。凹を刻む方法。削るハッチング。
クロスハッチング…その細線を交差させた重層や、色んな色線を重ねる事
マスキング…テープで支持面を保護し、保護されていない所だけに塗布する事。
ステンシル…その保護の計算織面仕様によって、模様を創る事。
デカルコマニー…張り合わせた絵の具の引きや型を使う、型押しモデリング。
フロッタージュ…物の型を起こす技術。
コラージュ…紙を張り合わせ、絵画にする、また絵画と一体化させる事。
アッサンブラージュ…立体物を張り合わせ、絵画にする、また絵画と一体化させる事。
ヒディング…下地の跡を少し隠し、その痕跡を魅力に変える技術。
モデリング…媒質塑形。状態は様々で、色々な状態が望める技術。「応物象形」
ポワリング…絵の具を垂らす技術。特殊なクセがいる。描写と中々噛みにくい。
アクションペインティング…絵の具を叩きつけたり、振り回したりする技術。
ドリッピング…絵の具の玉を振り落とす技術。前述した2つとは同種類になる。
透かし
暈し
ブラッシュストローク
ドライブラッシュ
基礎技術
着色(反復)ティンティング
着色(塗布)ペインティング
下図 エスキース
輪郭特定 プロフィリ
輪郭調整 コントリオーニ
下線主線確定 カルトーネ
彩色 カラーレ
キアロスクーロ(明暗画)
インパスト(上層厚塗り)
インプリマトゥーラ(有色下地)
グレージング(単色層)
カマイユ(有色下地上単色画)
グリザイユ(白~黒階調画)
エボッシュ(彩色下絵)
グラッシ(薄塗り重層画)
ハッチング(線描)
クロスハッチング(交差線描)
スカンブリング(仕上げ平塗り・技術)
ベラトゥーラ(仕上げ平塗り・表現)
ベラメンティ(仕上げ平塗り・細密化)
リリエーヴォ(盛り上げ効果)
プレパレーション(地塗り)
ヒディングパワー(色層力)
コンポジジション(色面バランス分割)
クロワゾネ(仕切り色面)
アラプリマ(直接描き ・喜踊躍動) primaria
模 イミテーション
再現 リプレゼンテーション
再復 レストレーション
復元 レノバティオ
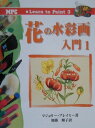
ハード島は荒涼として、起伏が多いのが特徴で、ビッグベン・マッシフにある2745メートルのモーソン・ピークなどに代表される。マクドナルド諸島は比較的小さく、岩で出来ているのが特徴である。それらすべての面積は412km²である。港はない。
諸島全体はオーストラリアの領土で、オーストラリア環境と遺産省(Australian Department of the Environment and Heritage)のオーストラリア南極局(Australian Antarctic Division)が管理している。島は環境保護のために保護され、研修者のみに公開されている厳正保護地域である。
島には経済活動が皆無であるのに国コードが与えられ、インターネットのドメインも .hm というものが与えられている。
ハード島とマクドナルド諸島は1833年11月27日イギリス人の度量衡検査官ピーター・ケンプが海域で島を見つけたのが始めとも言われる。これが正しければ、これが最初の人間によるこの島の認識である。ピーターはケルゲレンから南極への航海中、方位磁石で諸島を確認、その後島に降り立ったと言われている。
後にはオリエンタル号のキャプテン・ジョン・ハードがマサチューセッツ州ボストン市からメルボルンへの航海への途中で1853年11月25日、島を確認した。彼は1ヶ月後にこの島の発見を発表し、キャプテン・ジョン・ハードの発見した島はハード島と呼ばれるようになった。一方1854年1月4日にはサマラン号のキャプテン・ウイリアム・マクドナルドもこの海域で別の諸島を発見、これも彼の名前にちなみマクドナルド諸島と呼ばれた。
しかし、ハードもマクドナルドもこの諸島に降り立つことはなかった。ピーター・ケンプを別格にして、初めてこの島に降り立ったのは1885年3月、コリンシアン号のキャプテン・エラスムス・ダーウィン・ロジャーズである。その後、アザラシの脂(油)を取るために、アメリカ人がここへ住み着くようになったが、1880年までには彼らはすべて退散した。この間100,000バレルものアザラシの脂が生産されたという。

オーストラリアの不思議100
諸島全体はオーストラリアの領土で、オーストラリア環境と遺産省(Australian Department of the Environment and Heritage)のオーストラリア南極局(Australian Antarctic Division)が管理している。島は環境保護のために保護され、研修者のみに公開されている厳正保護地域である。
島には経済活動が皆無であるのに国コードが与えられ、インターネットのドメインも .hm というものが与えられている。
ハード島とマクドナルド諸島は1833年11月27日イギリス人の度量衡検査官ピーター・ケンプが海域で島を見つけたのが始めとも言われる。これが正しければ、これが最初の人間によるこの島の認識である。ピーターはケルゲレンから南極への航海中、方位磁石で諸島を確認、その後島に降り立ったと言われている。
後にはオリエンタル号のキャプテン・ジョン・ハードがマサチューセッツ州ボストン市からメルボルンへの航海への途中で1853年11月25日、島を確認した。彼は1ヶ月後にこの島の発見を発表し、キャプテン・ジョン・ハードの発見した島はハード島と呼ばれるようになった。一方1854年1月4日にはサマラン号のキャプテン・ウイリアム・マクドナルドもこの海域で別の諸島を発見、これも彼の名前にちなみマクドナルド諸島と呼ばれた。
しかし、ハードもマクドナルドもこの諸島に降り立つことはなかった。ピーター・ケンプを別格にして、初めてこの島に降り立ったのは1885年3月、コリンシアン号のキャプテン・エラスムス・ダーウィン・ロジャーズである。その後、アザラシの脂(油)を取るために、アメリカ人がここへ住み着くようになったが、1880年までには彼らはすべて退散した。この間100,000バレルものアザラシの脂が生産されたという。

オーストラリアの不思議100
カメルーン南東部の熱帯雨林、コンゴ北部、ガボン北部、中央アフリカ共和国南東部に住むピグミーの民族グループである (バンツー系)。
トワ・ピグミーの下位グループであるとしばしば誤解されるが、両者の間に密接な関係はない。同様にカメルーンの2から9の認められたピグミーの集団に誤用される。平均身長は1.5mであり、正確に言えばピグミーと言うよりもピグモイドである。にもかかわらず、日常的にピグミーの語が使われている。バカ族自身は「ピグミー」の語を軽蔑的とみなし、彼らの部族名を好んでいる。
コンゴ民主共和国とスーダンのバカ族とは関係はない。
人口
バカ族の正確な人口は決定し難く、5,000人から28,000人と推定されている。
言語
他の殆どのアフリカ中部のピグミー系諸族で独自の言語の残存が確認されておらず、バントゥー語系の周囲の農耕民の言語のみが用いられているのと異なり、バカ族はバカ語と呼ばれる独自の言語を保持し、それはニジェール・コンゴ語族アダマワ・ウバンギ語派に属する。また、多くのバカ族は隣接するバントゥー系の言語Koozimeも第二言語として用いる。少数はフランス語を話す。
生活
バカ族は狩猟採集民である。グループは折り曲げた枝に大きな葉を被せた小屋(しかし今日次第にバンツー族の方式の家になりつつある)で一時的なキャンプを行なう。男達は周辺の森で、毒矢や毒槍を用いた狩をし、獲物を罠で捉える。一方女達は果物や木の実を集めるか、子供の世話をしていれば養蜂を行なう。グループは狩が成功するまで一つの場所に留まり、その後そのキャンプを捨てて森の別の場所へ移る。原始共産制で、意見の一致により物事を決定する。
信仰
バカ族はアニミズムを行ない、祖霊にして守護者とされるジェンギという森の聖霊を信仰している。 狩が成功した後にルマという太鼓と合唱を伴なった感謝の踊りが行なわれる。他の伝統行事には男子の成人の儀式ジェンギ(前述の聖霊とは異なる)がある。バカ族には独自の伝統医学があり、部族以外の者でもピグミーの治療者を探す程である。
バカ族は隣接して住むバンツー族と共生関係にあり、交易を行なうためによく道沿いにキャンプを構え、物々交換を行なう。バカ族は通貨経済に大部分がまだ慣れていないため、他の部族によるバカ族の搾取は重大な現実である。時に他の部族がバカ・ピグミーを労働者として雇うが、実際一日分の給料が支払われないことがある。また、観光を意識して、多くのバカ族以外の人間がピグミーの村を訪れたり、留まったりする手筈を整え、自然保護林を訪れる人へバカ族のガイドを雇うが、しばしばバカ・ピグミーへの報酬は僅かである。バカ族とバンツー族の部族間結婚の率は上昇している。バカ族は他の民族と日常的に結婚し、他民族の配偶者のライフスタイルを採り入れるため、何人かの学者はいつかバカ・ピグミーが他の民族と完全に同化してしまうだろうと予測している。
バカ族はカメルーンや周辺の国々で最も古くからの住民の一つである。半ば放浪生活を行なう彼らの生活様式は植民地主義のさなか、彼らの象狩りの能力に眼をつけた象牙に飢えたドイツ・フランスの領主が彼らを利用しやすいよう道沿いの村に住まわせた事実にもかかわらず、何千年もの間変わらなかった。カメルーンの政府は報奨金と全ての子供への学校教育の義務を通してこの方針を保持しようとした。しかしバカ族の大部分は従っていない。今日彼らの生活への最大の脅威は森林伐採であり、森が消えれば、バカ族の依存する動物と植物も同様に消える
トワ・ピグミーの下位グループであるとしばしば誤解されるが、両者の間に密接な関係はない。同様にカメルーンの2から9の認められたピグミーの集団に誤用される。平均身長は1.5mであり、正確に言えばピグミーと言うよりもピグモイドである。にもかかわらず、日常的にピグミーの語が使われている。バカ族自身は「ピグミー」の語を軽蔑的とみなし、彼らの部族名を好んでいる。
コンゴ民主共和国とスーダンのバカ族とは関係はない。
人口
バカ族の正確な人口は決定し難く、5,000人から28,000人と推定されている。
言語
他の殆どのアフリカ中部のピグミー系諸族で独自の言語の残存が確認されておらず、バントゥー語系の周囲の農耕民の言語のみが用いられているのと異なり、バカ族はバカ語と呼ばれる独自の言語を保持し、それはニジェール・コンゴ語族アダマワ・ウバンギ語派に属する。また、多くのバカ族は隣接するバントゥー系の言語Koozimeも第二言語として用いる。少数はフランス語を話す。
生活
バカ族は狩猟採集民である。グループは折り曲げた枝に大きな葉を被せた小屋(しかし今日次第にバンツー族の方式の家になりつつある)で一時的なキャンプを行なう。男達は周辺の森で、毒矢や毒槍を用いた狩をし、獲物を罠で捉える。一方女達は果物や木の実を集めるか、子供の世話をしていれば養蜂を行なう。グループは狩が成功するまで一つの場所に留まり、その後そのキャンプを捨てて森の別の場所へ移る。原始共産制で、意見の一致により物事を決定する。
信仰
バカ族はアニミズムを行ない、祖霊にして守護者とされるジェンギという森の聖霊を信仰している。 狩が成功した後にルマという太鼓と合唱を伴なった感謝の踊りが行なわれる。他の伝統行事には男子の成人の儀式ジェンギ(前述の聖霊とは異なる)がある。バカ族には独自の伝統医学があり、部族以外の者でもピグミーの治療者を探す程である。
バカ族は隣接して住むバンツー族と共生関係にあり、交易を行なうためによく道沿いにキャンプを構え、物々交換を行なう。バカ族は通貨経済に大部分がまだ慣れていないため、他の部族によるバカ族の搾取は重大な現実である。時に他の部族がバカ・ピグミーを労働者として雇うが、実際一日分の給料が支払われないことがある。また、観光を意識して、多くのバカ族以外の人間がピグミーの村を訪れたり、留まったりする手筈を整え、自然保護林を訪れる人へバカ族のガイドを雇うが、しばしばバカ・ピグミーへの報酬は僅かである。バカ族とバンツー族の部族間結婚の率は上昇している。バカ族は他の民族と日常的に結婚し、他民族の配偶者のライフスタイルを採り入れるため、何人かの学者はいつかバカ・ピグミーが他の民族と完全に同化してしまうだろうと予測している。
バカ族はカメルーンや周辺の国々で最も古くからの住民の一つである。半ば放浪生活を行なう彼らの生活様式は植民地主義のさなか、彼らの象狩りの能力に眼をつけた象牙に飢えたドイツ・フランスの領主が彼らを利用しやすいよう道沿いの村に住まわせた事実にもかかわらず、何千年もの間変わらなかった。カメルーンの政府は報奨金と全ての子供への学校教育の義務を通してこの方針を保持しようとした。しかしバカ族の大部分は従っていない。今日彼らの生活への最大の脅威は森林伐採であり、森が消えれば、バカ族の依存する動物と植物も同様に消える
そのほとんど全ては発症原因がわかっていない。唯一の例外がリウマチ熱であったが、現代ではまれな疾患になっている。したがって治療方針は対症療法になる。
リウマチ科の扱う疾患は免疫が大きな役目を果たしており、免疫の力を弱める薬が治療において有用である。その為、ステロイドや、癌の治療にも使われる免疫抑制薬(メソトレキセート、タクロリムス)などが免疫力を弱める薬としてリウマチ科でも利用されている。
20世紀末頃から、分子レベルまで解明された病態生理学を利用して、分子レベルで疾患をおさえにかかる薬も現れている。現在はリコンビナント技術を用いて特定のサイトカインネットワークを遮断する試みがうまくいき、次々と新薬が投入されている。特に目覚しいのが関節リウマチであり、インフリキシマブ、エタネルセプトなど次々と効果の大きい新薬が使用開始されている。インフリキシマブ(Infliximab)は、難治性の多くの関節リウマチ患者に劇的な治療効果を示すのみならず、強直性脊椎炎などその他の疾患にもその治療応用を広げている。
しかし、リウマチ・膠原病に関しては、疾患群として巨大であり、先進諸国の資金援助が豊富に受けられる医療分野でありながら、21世紀に入ってもこの疾患が起る原因の手がかりはつきとめられておらず、治療は全て発症後の対症療法であって、リウマチ・膠原病患者のほとんどは、治療のために薬を一生のみ続けることを強いられる。これら多くの薬剤も病気を完全になくすことはできず病気の真の発生機序とそ治療法の発見がのぞまれる。
語源
リウマチとは、古代ギリシャにおいて「ロイマ(Rheuma、流れの意)」という言葉から発生したもので、このころの人々は脳から体液が下のほうに流れ、うっ滞すると腫脹や発赤をきたすと考えられており、体の中の悪い液体が疾患を引き起こしているという考えに基づいたものである言われている。ロイマrheumaという言葉は少なくとも西暦100年ころには使用されていたという。またこの頃インドでは、すでに関節リウマチの臨床所見を正確に記載した文献が出ている。

リウマチ科の扱う疾患は免疫が大きな役目を果たしており、免疫の力を弱める薬が治療において有用である。その為、ステロイドや、癌の治療にも使われる免疫抑制薬(メソトレキセート、タクロリムス)などが免疫力を弱める薬としてリウマチ科でも利用されている。
20世紀末頃から、分子レベルまで解明された病態生理学を利用して、分子レベルで疾患をおさえにかかる薬も現れている。現在はリコンビナント技術を用いて特定のサイトカインネットワークを遮断する試みがうまくいき、次々と新薬が投入されている。特に目覚しいのが関節リウマチであり、インフリキシマブ、エタネルセプトなど次々と効果の大きい新薬が使用開始されている。インフリキシマブ(Infliximab)は、難治性の多くの関節リウマチ患者に劇的な治療効果を示すのみならず、強直性脊椎炎などその他の疾患にもその治療応用を広げている。
しかし、リウマチ・膠原病に関しては、疾患群として巨大であり、先進諸国の資金援助が豊富に受けられる医療分野でありながら、21世紀に入ってもこの疾患が起る原因の手がかりはつきとめられておらず、治療は全て発症後の対症療法であって、リウマチ・膠原病患者のほとんどは、治療のために薬を一生のみ続けることを強いられる。これら多くの薬剤も病気を完全になくすことはできず病気の真の発生機序とそ治療法の発見がのぞまれる。
語源
リウマチとは、古代ギリシャにおいて「ロイマ(Rheuma、流れの意)」という言葉から発生したもので、このころの人々は脳から体液が下のほうに流れ、うっ滞すると腫脹や発赤をきたすと考えられており、体の中の悪い液体が疾患を引き起こしているという考えに基づいたものである言われている。ロイマrheumaという言葉は少なくとも西暦100年ころには使用されていたという。またこの頃インドでは、すでに関節リウマチの臨床所見を正確に記載した文献が出ている。

